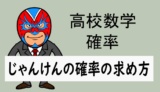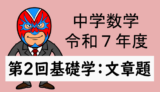こんにちは。今回の基礎学は要所要所で難しい問題があり,解きにくかったのかなと感じている次第です。それでは平面図形の問題やってみましょう。例のごとく相似,三平方の定理は未修ということで話を進めていきます。
下の図のように,正方形ABCDの対角線ACの延長上に点Eをとり,線分DEをひく。線分DEを1辺とする正方形DEFGをつくり,点G,点C,点Eをそれぞれ結ぶ。次の(1)~(3)に答えなさい。
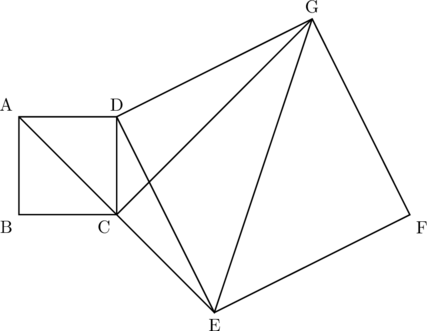
(1)
(2)
(3)
(1) ![]() と
と![]() において,
において,
仮定より,![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ,
,![]() より,
より,![]()
![]() ,
,![]() ,
,![]() より,2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので,
より,2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので,![]()
(2) ![]()
(3) ![]()
【解説】
(2) 三角形の外角はその隣にない2つの内角の和に等しいので,![]()
ACは正方形の対角線より,![]() ,また,
,また,![]() より
より![]() は,
は,![]()
よって,![]()
(3) 三平方の定理は未修ということで解説します。
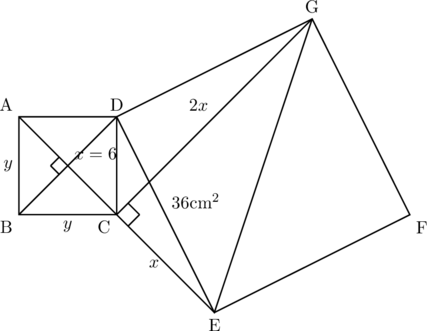
また,(1)より,
正方形ABCDの面積は
※正方形の面積は(対角線)
よって,
※三平方の定理で習う三角形の辺の比を知っていれば,
 数樂管理人のブログ
数樂管理人のブログ